【会報】海夫通信49号発行しました
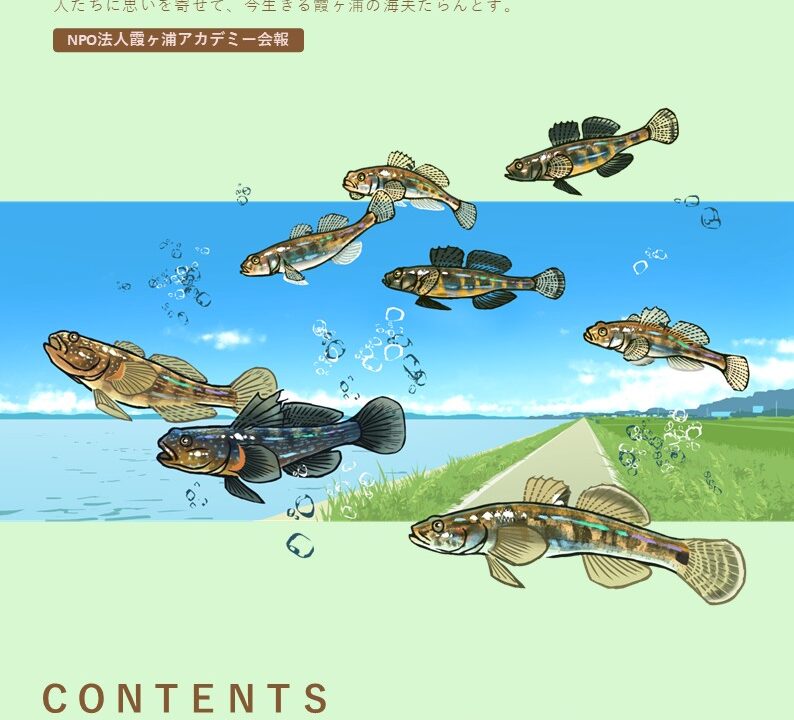
NPO法人霞ヶ浦アカデミーの会報「海夫通信」49号を2025年8月に発行しました。
2008年の設立から発行しており、今回で49号となりました。以下にコンテンツの一部を紹介いたします。詳細はリンクのPDFファイルをご覧ください(画像をクリック!)。

霞ヶ浦北浦 歴史的不漁の謎を解く その3 原因解明に挑戦(濱田篤信)
今回は漁獲変動を4グループに分けてみました。
- 1次消費者:植物を食べる種、植物を直接利用、摂取する貝類やハクレンなど。動物プランクトンも入ります。
- 2次消費者:動物プラン食者のワカサギ、シラウオ、クルメサヨリ。イサザアミも漁獲変動がワカサギに近いので、この仲間にいれました。
- 肉食種:ウナギ、ナマズとスズキが該当しますが、ニゴイもこの仲間に加えました。外来魚ではライギョ(カムルチー)、オオクチバスです。
- 雑食種:コイやギンブナ、ドジョウ、ヌマチチブですが、エビ類、タナゴ類も、同傾向の漁獲変動を示しているので雑食性と考えられます。漁獲変動の傾向は、若干ちがいますが、ウグイ、ヒガイもこのグループに加えました。
魚類生産を消費された有機物量に変換する栄養段階の数
魚類の単位生産当たりの有機物消費量は食性によって異なります。一次消費者では、直接、植物を消費するので栄養段階の数は以上に示したようにですが、ワカサギやシラウオでは、植物プランクトンを消費した動物プランクトンを利用するので栄養段階数は2です。エビやハゼ類、コイ、フナは雑食性で主にデトリタス(分解過程にある有機物)を摂食しますが、底生動物や動物プランクトンも摂食するので栄養段階の数は一次と二次消費者の中間の1.5程度です。
(中略)
1900年から現在に至る一世紀の漁獲量変動は、1960年の時点で前後に大別されました。さらに後期(1960年から現在)は好気的分解によって漁獲量が増大した1960~1975年の増大期、好気から嫌気的代謝へ遷移が進む代謝遷移期(1975~1985)および嫌気的代謝定着期(1985~現在)に分画することができます。1960年、1975年および1985年はそれぞれ常陸川水門建設開始、常陸川水門暫定管理開始および暫定操作影響定着時に相当します。
底層の酸素濃度は水深4.5m前後で急激に低下しますが、そのことによって底層における有機物の分解が好気から嫌気的分解に推移します。バクテリアによる有機物の分解過程では高エネルギーリン化合物のATPが生成されますが、これがバクテリアの増殖やデトリタス生成の原動力となります。有機物分解過程でのATP生成率を比較すると、嫌気的過は好気のそれの2/38、すなわち約1/20に過ぎません。このことが現在の漁獲量が再生期の約1/20にまで低下した原因と考えられます。
(本誌で全文をお読みいただけます)。
霞ヶ浦 歴史散歩②(S・H)
今回のテーマ: 霞ヶ浦がもたらした脅威 玉造に残る洪水の遺構
霞ヶ浦は、人々の生活に恵みをもたらす一方、度重なる洪水で周辺地域に被害をもたらす存在でもありました。今回は、玉造に残る洪水の遺構をたどります。江戸時代初期、徳川家康の命で、東京湾に注ぐ利根川の流路を、銚子沖へと変える大改修工事、「利根川の東遷」が行われました。これにより、霞ヶ浦は利根川と繋がり、水運が大きく発展します。一方で、この工事は、霞ヶ浦の水の出口を狭めてしまう結果となり、周辺地域では洪水が頻繁に起こるようになりました。
さらに1783年の浅間山噴火で、利根川に大量の土砂が流出し、霞ヶ浦から利根川への水の流れを塞ぐようになります。霞ヶ浦からの流出水量は激減し、霞ヶ浦の水位は、少量の雨でも上がりやすくなってしまいました。1950年までの167年間でおよそ70回、それまでの約3倍の頻度で水害が起こるようになったといいます(注1)。
こうした中、現在の霞ヶ浦大橋のたもと、高須に、私財を投じておよそ2㎞の堤防を築いたのが、里正(名主)の白井小右(こ)衛門(えもん)です。築堤には、1806(文化3)年(1820(文政3)年とも)から3年を費やしたと伝わります。堤防の頂部(天端(てんぱ))は、高須の町中を通る道路となっており、脇に立つ築堤回向の碑(1826(文政9)年建立)が、痕跡を残しています。
霞ヶ浦の大きな洪水は、明治から昭和初期にかけても起こりました。「道の駅たまつくり」向かって右側湖岸にある「洪水の碑」は、台風通過とそれに刺激された梅雨前線の降雨がもたらした1938(昭和13)年6~7月の水害を伝える自然災害伝承碑で、1989(平成元)年に建立されました。碑は、この洪水で台石に引かれた赤線の下1mまで湖水位が上がり、利根川改修工事開始以来、最高水位になったと伝えています。
注1 茨城県 霞ヶ浦関連資料「霞ヶ浦入門」第2章「霞ヶ浦と人との関わり」第4回「霞ヶ浦と人との関わりの変遷」(令和4年10月17日)より

